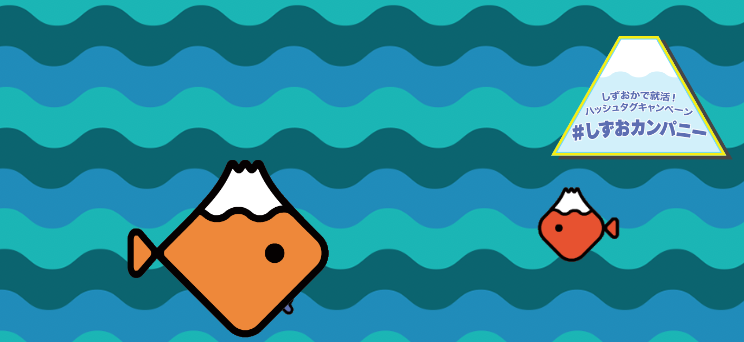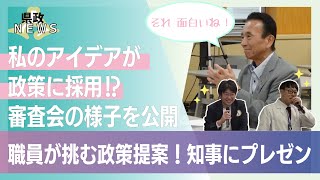フカボリ
空の移動革命へ : 次世代エアモビリティの可能性と展望
2025年2月19日
交通渋滞に巻き込まれ、なかなか前に進まないとき、「空を飛んで移動できたら・・・」。そんな夢を抱いたことがある方も多いと思います。空を飛んで移動することが今、現実になろうとしています。今回のフカボリは、飛行機やヘリコプターとは違い、タクシーのように日常生活に馴染みのある移動手段として開発が進められている、次世代エアモビリティ(eVTOL)の魅力をお伝えします。
「県民だより」3月号と併せてご覧ください。
県民だより3月号 https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/pr/johoshi/kenmin/1061761/1069804/1069806.html
目次
- 静岡県と朝日航洋が連携!3次元点群データで実現する未来の空の移動
- 空飛ぶクルマの未来 : 次世代エアモビリティ(eVTOL)の操縦と安全性に迫る
- 静岡県の空に広がる未来!次世代エアモビリティ(eVTOL)の可能性と魅力
1.静岡県と朝日航洋が連携!3次元点群データで実現する未来の空の移動
今、全国各地で次世代エアモビリティの導入に向けた動きが活発になってきています。本県は、2024年12月に、「次世代エアモビリティ導入促進(eVTLOL)のロードマップ」を公表しました。
このロードマップの公表に先立って、2023年8月には、朝日航洋株式会社と「次世代エアモビリティ分野における3次元点群データ※1 の利活用に関する連携協定」を締結しました。
今回、朝日航洋株式会社※2 航空事業本部 エアモビリティ事業部の茨木さんにお話を伺いました。

- ※1 3次元点群データ:1点ごとに緯度、経度、標高の3次元の位置情報を持つ点の集まり。航空レーザ測量と車両にレーザスキャナを搭載したMMS(モービルマッピングシステム)による地上からの計測を組み合わせて活用できるようにした。県内全域のデータが揃っており、データの質が高い。VIRTUAL SHIZUOKAポータルサイトで公開中(誰でも自由にダウンロード可能)。
- ※2 朝日航洋株式会社は、2025年7月1日、「エアロトヨタ株式会社(英文表記:AERO TOYOTA CORPORATION)」に社名変更します。
ー2023年8月に協定を締結したきっかけを教えてください。
協定締結のきっかけは、静岡県が実施した3次元点群データの整備において、県土の航空レーザ測量を担ったことでした。この3次元点群データの新たな利活用の展開として、次世代エアモビリティ分野をご提案させていただき連携協定締結との運びとなりました。弊社は、3次元点群データなど地理空間情報を取り扱う空間情報事業だけではなく、ヘリコプターの運航を中心とした航空事業を展開しております。地理空間情報と航空事業の豊富な知見により、次世代エアモビリティ(eVTOL)が離着陸できる適地はどこか、どのような航路がふさわしいかなどの検討を進める上で、関わることができると考えています。
ー次世代エアモビリティ(eVTOL)については、2024年11月にトヨタ自動車株式会社とJoby Aviation社が裾野市で試験飛行を実施しました。この試験飛行に御社も関わったと聞きました。
はい。この機会は、Joby Aviation(以下、Joby)の国内初飛行であり、静岡県内での次世代エアモビリティ(eVTOL)の初飛行となるものでした。当日、Jobyにより飛行が行われ、弊社は、Jobyが国内で飛行するための申請(航空法)や飛行時の無線利用の申請(電波法)の面で協力しました。

▲飛行映像:https://youtu.be/h2bBbdRyd_8?feature=shared(出典:トヨタ自動車)
2.空飛ぶクルマの未来:次世代エアモビリティ(eVTOL)の操縦と安全性に迫る
ー次世代エアモビリティ(eVTOL)は、電動なので騒音が少なく、環境にも優しいので、利用者目線でも生活に溶け込みやすい印象があります。パイロット側の視点では、どちらが運転しやすいと思いますか?
現在、次世代エアモビリティ(eVTOL)で型式証明がなされた機種はなく、開発段階なので明確なことは言えませんが、ヘリコプターは両手両足を使って操縦するのに対し、次世代エアモビリティ(eVTOL)はレバーを中心とした飛行になると言われているので、ヘリコプターよりも操縦しやすくなると想像しています。さらに最終的には自動操縦でフライトが可能なように開発が進められていると聞いております。
ただ、例えば突然の強風のときには、ヘリコプターの方がパワーがあるとともに、これまでさまざまな天候シーンで安全に飛んできたという実績もあるので安全性・信頼性が高いのが現状です。次世代エアモビリティ(eVTOL)の技術革新により、解決できる問題もあると思うので、今後の発展に期待しています。私共としては、ヘリコプターの運航も行ってきたので、利用シーンに応じて、ヘリコプターと次世代エアモビリティ(eVTOL)との使い分けができることも強みと考えています。
ー飛行中、モーターが駆動しなくなったらどうなるのでしょうか?
私共はメーカーではなく運航事業者的立場なので明確には答えることはできないのですが、機体メーカーさんも安全対策を検討した上で設計しています。そもそも、国の基準にのっとり、安全が確立された中で開発され、最終的には機体の型式の証明、認可されるものになり、現在、機体メーカーさんと国とで進められているところです。私共としては、安全な機体が世の中に生まれてくることを期待しているとともに、安全に合致したものを航空法に合わせて適切な方法・手段で運航対応していきたいと思っています。
ー飛行時に、次世代エアモビリティ(eVTOL)同士がぶつかってしまう可能性はあるのでしょうか?
これから航空法で運航のルールが定められていくと思います。ルールを守って適切に飛ばせば、事故を回避できるのではないかと思っています。
次世代エアモビリティ(eVTOL)のことを、国では『空飛ぶクルマ』とも呼んでいます。空飛ぶクルマ、というと、「自動車に羽が生えて空を飛ぶ」、「自家用車のように自分の好きな場所へ思い思いのルートで空を飛ぶことができる」といったイメージを抱く方も多いと思いますが、そうではありません。分類としては自動車ではなく、航空機の分類になります。現在、自動車は日常生活と密接に関わりがあり、誰もが利用するものになっています。次世代エアモビリティ(eVTOL)も自動車のように、空の移動手段として身近なものとなってほしい、という願いから、空飛ぶクルマ、と呼ばれています。
実際に運航する際には、決まった航路、空域での飛行になると思いますので、今後の運行ルールが定められていくのを見守っていきたいと思います。
3.静岡県の空に広がる未来!次世代エアモビリティ(eVTOL)の可能性と魅力
ー本県の利点や特色をどのようなところに感じていますか?
静岡県は、次世代エアモビリティ(eVTOL)を活用できるポテンシャルが高いと思います。富士山、伊豆、南アルプス、浜名湖…と国内外から見て、観光的に魅力的な要素が多くあり、さらに盛り上げることにもつながると思います。例えば、富士山静岡空港から富士山方面に観光に行きたいというニーズがあるので、次世代エアモビリティ(eVTOL)が普及する可能性は高いと思っています。
また、大都市圏と比べると次世代エアモビリティ(eVTOL)を飛ばしやすい環境にあります。大都市圏では高層ビル・マンションなどが多く、空域の密度が高いので、どうやって飛ばすか、という課題があります。その点、静岡県内は、空域を活用しやすいので、普及する要素は大きいと思っています。
ー首都圏ではビルの屋上を離着陸場に使えそうなイメージがあり、飛ばしやすそうな印象を持っていました。
実は、ビルの屋上を離発着場にするには、課題があります。ビル屋上自体の強度の問題、次世代エアモビリティ(eVTOL)を充電できる電源環境や消火施設の整備、離着陸可能な広さの確保、周辺構造物との安全確保などを解決しなければなりません。一見、簡単そうに見えますが、細かく見ていくと厳しいという印象を持っています。
ー次世代エアモビリティ(eVTOL)の魅力をどのようなところに感じていますか?
敷居が高いと思われていたヘリコプターよりも個人利用の視点で、技術革新の可能性を秘めています。商用運航開始時は機体価格は高いかもしれませんが、普及し量産化され始めれば価格が下がってくる可能性もあります。そうすれば、運航コストも下がってくる要素があります。誰でも乗れるもの、という個人利用のポテンシャルが高いと思っています。
ー大阪万博でも飛行が予定されています。将来、どのようなことを期待していますか?
大阪万博では、デモフライトが実施され、人々の注目が集まります。機体の開発や運航のルール等の基準策定が進み、少しでも早く、人が乗っての移動が現実になることを期待しています。
弊社としても、次世代エアモビリティ(eVTOL)の商用運航を目指しています。全国の空を飛ぶ時代を培っていきたいと思います。ヘリコプターの次の乗り物として、次世代エアモビリティ(eVTOL)の運航を担っていきたいと思っており、期待に応えるべく、われわれも進化してきたいと思います。
取材を終えて
新たな交通手段としての次世代エアモビリティ(eVTOL)、少々遠い存在であった空の移動が身近に感じられました。数年後には実際に乗ることができる機会が出てくるかもしれません。今後、どのように技術革新がなされていくか、とても楽しみになりました。
県民だより3月号 https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/pr/johoshi/kenmin/1061761/1069804/1069806.html
―――↓問い合わせ――――――――――――――――――――――――――
【問い合わせ】 県広聴広報課 054(221)2231 FAX054(254)4032