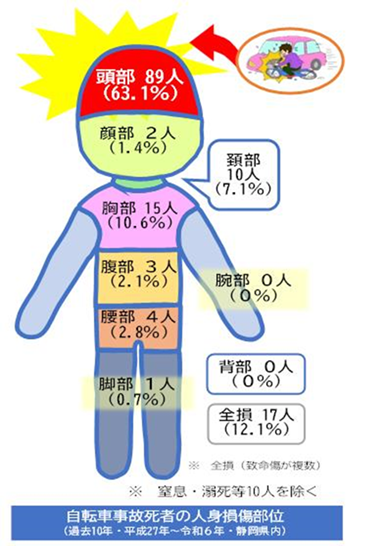フカボリ
伝統工芸の魅力を世界に発信!匠宿の魅力
2025年4月30日
県民だより5月号2面にて、4月13日(日)に開幕した大阪・関西万博を特集しています!6月6日(金)から8日(日)までの3日間は万博会場に静岡県ブース「GEO KITCHEN SHIZUOKA」を出展するため、県民だよりでその魅力を紹介しています。
今回は、静岡県ブースでワークショップを開催する、静岡市駿河区丸子の「駿府の工房 匠宿」を取材してきました。「駿府の工房 匠宿」は静岡市の工芸体験施設で、駿河竹千筋細工や和染などさまざまな体験ができます。伝統工芸というと、ちょっと敷居が高いと感じる方もいるかもしれませんが、匠宿の周辺には海外からの旅行客の姿もあり、たくさんの方でにぎわっていて興味が高まります!今回お話を伺ったのは、館長の杉山浩太さんと竹と染工房長で、お茶染めに取り組む鷲巣恭一郎さんです。

目次
1. 「駿府の工房 匠宿」とは?
館長)伝統工芸を体験できる静岡市の施設です。2021年のリニューアルから、株式会社創造舎が運営しています。一般のお客様の体験はもちろんできますが、匠宿には職人の工房があり、体験内容の充実はもちろん、ものづくりの現場、職人育成の場となっています。また、匠宿は周辺地域の活性化プロジェクトにも取り組んでいて、宿やレストランをはじめ、地域一帯の魅力に工芸という要素を取り入れている段階です。
全国にも工芸体験の施設はありますが、匠宿の特徴として駿河竹千筋細工、和染、木工、漆塗、陶芸、模型など多様な体験ができます。このような複合的な施設は珍しいんです。
―カフェやレストランもありますね。
館長)はい。ここでは、伝統工芸で彩った空間でお茶を飲めたり、食事も楽しめます。体験だけではなく、匠宿全体で工芸に触れることができます。
―先ほど、職人育成の場でもあるとおっしゃっていました。
工房長)弟子もいます。この4月からも新しく二人目が入りました。日中は工芸体験のインストラクター、夜は自分の作品を作るといった人もいます。職人と弟子のような、一対一の関係だけではなく、この施設のスタッフなどいろいろな方と関わることができるのも特徴です。さまざまな業種から入ってくる方がいますね。

ー伝統工芸の魅力は何でしょうか。
館長)静岡という土地柄はありますね。徳川家康が隠居の地として選んだこの地に、全国から職人が集まってきた。だから、静岡の伝統工芸の特色は、全国のいいところが集まっているとも言えます。駿河竹千筋細工は、実は静岡独自のものです。静岡は丸ひごを使いますが、武士が内職で作っていたので、世に出ていない。日本で唯一の技法が残っているんです。鷲巣さんがやられているように、静岡の産業と伝統工芸が結びついているものもあります。
工房長)染め物など伝統的なものの魅力は、やはりその土地の歴史や時間軸が地続きになっている点です。私はお茶染めをやっていますが、それも先人の技術を応用したものです。人の営みと一体となって広がっていくところが、伝統工芸の魅力だと思います。しかし、伝統工芸品は作れば売れるというものではありません。やはり自分がわくわくするようなものを作り続けることが大事だと思います。
2. 万博に向けて
―万博ではどのようなワークショップを開催しますか。
工房長)万博では来場者にお茶染め体験をしていただきます。静岡茶は飲むだけではない、という所を提案できるかなと思っています。一番の特徴は、お茶の製造工程で出る商品にならない部分を使って製品ができる、という点です。製造工程ではじかれてしまったお茶や粉末の部分を使用して染めます。染め物で使用したお茶がらは、堆肥として利用します。お茶というと、「飲む」という視点で見ますが、最近は茶畑をやめてしまうなど、問題もあります。しかし、先人が植えた茶畑が、もう一度価値のあるものに変わってくる、お茶でできる伝統技術がある、というところを知ってもらえたら、資産としての茶畑になると思います。
―万博に来る方や、世界中の方に発信したいことは何ですか。
工房長)先ほども話しましたが、お茶染めは製造工程ではじかれたお茶を使用し、それが商品になる。飲用として流通できない茶葉にも価値が付き続けます。特に、インバウンドの方の関心が高く、リアクションがありますね。お茶染めのマフラーを気に入ってずっと身に付けて下さっている海外の方もいらっしゃいます。循環がポイントとなるこの取り組みを発信していきたいと思います。

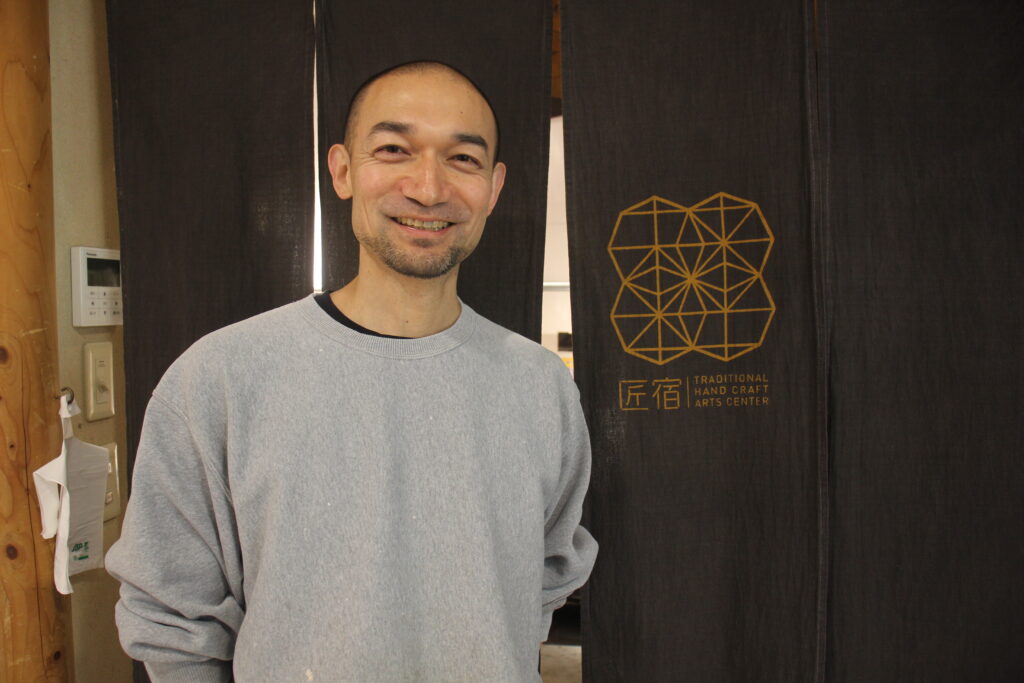

―今後の目標を教えて下さい。
館長)匠宿は体験だけでなく、商品の販売や展示も魅力です。カフェやレストランなど、いろいろな人が長い時間楽しめる仕組みができていて、匠宿から静岡の魅力が伝わるといいなと思います。工芸をきっかけとして、匠宿の周辺も含めて、みなさんに興味を持っていただけるような魅力的な場所にしていきたいと思います。
工房長)匠宿のあるこの地域を職人村として、担い手を育てていきたいと思っています。このエリアで生産力を向上させて、地域の大事なコンテンツにできればと思います。匠宿は、山奥で師匠と弟子だけで黙々と作業をするような環境とは異なり、施設で働きながら工芸に関わることができたり、匠宿にいる様々な価値観の人と関わることで社会性も身につけられたり、人を育てるには興味深い環境だと思います。それから、お茶ですね。資産として付加価値を付けられるような活動を進めていきたいです。


3. 県民の方へメッセージ
―最後に、県民の方にメッセージをお願いします。
館長)静岡県の皆さまにとって、誇れる場所となることを目指しています。職人さんなどの作り手、買って下さる使い手、そしてその間をつなぐ伝え手としての匠宿のスタッフと、バトンは続いています。静岡を楽しくしたい、盛り上げたいという気持ちでやっていますので、ぜひ一度お越し下さい。
工房長)お茶染めを「文化」にしたい、という目標があります。私の中の「文化」の定義は、地元の人たちが当たり前と思っていて、誇らしいと思っている状態です。私はお茶染めのレシピも公開していますし、いろいろな人と関わって広げていきたいと思っています。静岡県のみなさんが当たり前と思って誇らしく思ってくれるような活動をしていきたいと思っていますので、応援していただけたらうれしいです。
4. 最後に
匠宿は体験できるだけではなく、伝統工芸品に実際に触れる、使う、見て楽しむことができる施設だと感じました。職人さんたちが作業されている工房では、作業する音、匂いも感じることができ、伝統工芸がより近くに感じられます。取材中も、実際に数々の工芸品を見ることができました。エントランスに入らせていただいた際、駿河竹千筋細工の繊細さと美しさに圧倒されました。また、お茶染めの布の自然な風合いはずっと使いたくなるような、温かみがありました。工芸品の良さを近くで感じることができるのは、一度来たら分かる匠宿ならではの魅力です!
万博の静岡県ブースでは、取材させていただいた工房長の鷲巣さんがワークショップを開催します。魅力満載の大阪・関西万博や静岡県ブースの情報は、県民だより5月号でチェックしてみてください。
県民だより5月号関連記事URL:
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/pr/johoshi/kenmin/1070652/1071720/1071724.html
静岡県ブース公式サイト「GEO KITCHEN SHIZUOKA」
https://geo.shizuoka-gastronomy.jp/
駿府の工房_匠宿 公式サイト
―――問い合わせ――――――――――――――――――――――――――
【問い合わせ】 県広聴広報課 054(221)2231 FAX054(254)4032