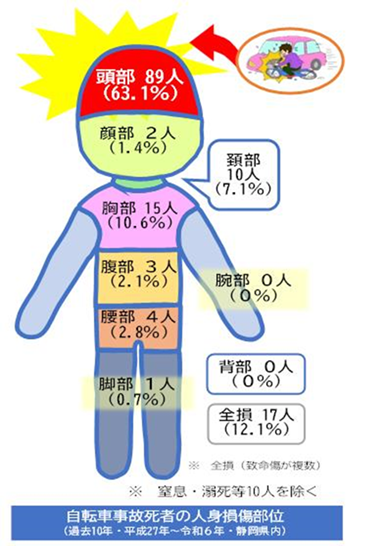フカボリ
静岡の教育の未来を描く――次期「教育振興基本計画」に向けた動き
2025年11月19日
こんにちは、ふじのくにメディアチャンネル学生特派員の大石凜里花です。
令和7年3月に「静岡県教育大綱」が策定されました。
この大綱の基本理念や取組方針をもとに、今後の教育の方向性を示す次期「静岡県教育振興基本計画」が、今年度中に策定される予定です。
現在の「静岡県教育振興基本計画(2022~2025年度)」は、静岡県公式ホームページで公開されています。
◆教育振興基本計画|静岡県公式ホームページ
次期計画の策定にあたり、県総合教育課と県教育委員会教育政策課はこども・若者からの意見を聞くためワークショップを開催しました。
今回は、県立磐田南高校(定時制)で行われたワークショップの様子を取材しました。

▽目次
1.こども・若者から意見を聞くためのワークショップとは
次期「静岡県教育振興基本計画」の策定にあたり、県総合教育課と県教育委員会教育政策課では、こども・若者の意見を直接取り入れるためのワークショップを実施しました。
特に、オンラインプラットフォーム「こえのもりしずおか」を利用しにくい環境にある、外国にルーツをもつ児童生徒や、障がいのある児童生徒の声を聴くため、県の職員が学校や関係機関を直接訪れています。
オンラインプラットフォーム「こえのもりしずおか」とは
こどもや若者の声を集め、施策に反映させることを目的に静岡県が設置しているオンラインプラットフォームです。
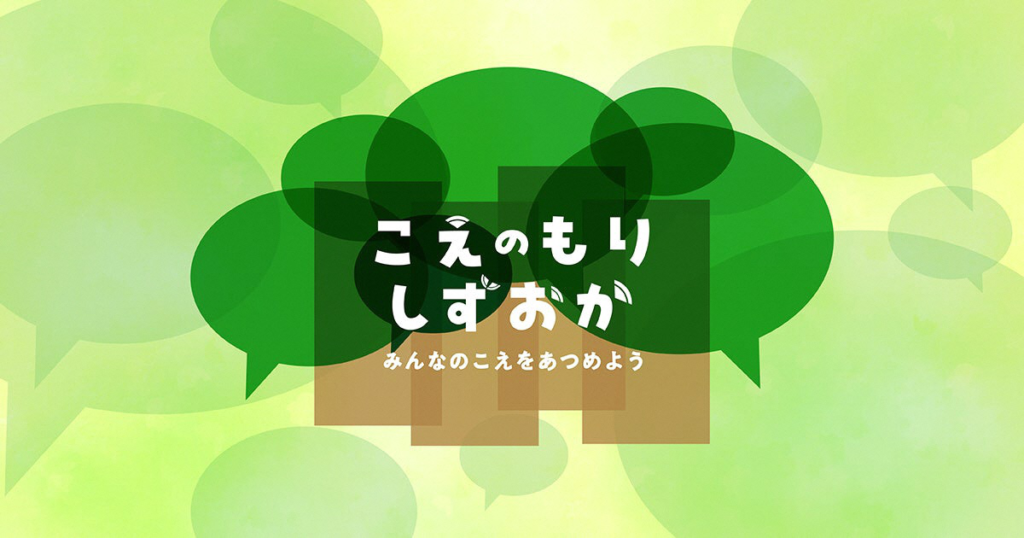
2.ワークショップの流れ
ワークショップの冒頭では、職員の方から、実施の目的や思いについて説明がありました。
今回の磐田南高校(定時制)では、外国にルーツをもつ生徒が参加しており、資料は英語に加えて、わかりやすい表現を用いた「やさしい日本語」でも作成されていました。

その後、学年ごとに3つのグループに分かれ、各グループに職員が1名ずつ入りました。
「将来こんなことがしたい」「こんな人になりたい」というテーマをもとに、自由に意見を交わしました。
職員の方が優しく質問を投げかけると、生徒たちは自分の夢や思いをしっかりと伝えていました。
3.生徒の声 ~グループワーク~
グループワークでは、生徒たちの率直で温かい言葉が飛び交いました。
将来の夢としては、
「料理が好きだから、料理人になりたい」
「いろいろな国に行ってみたい」
など、明るい表情で話す姿が印象的でした。
一方で、「言葉の壁」に関する声も多く聞かれました。
「中学時代は、教科書に読み仮名がなく理解が難しかった」
「漢字にはいろいろな意味があって、今でも苦労している」
といった経験を、それぞれが丁寧に語ってくれました。
また、「もっと多くの人と関わる機会がほしい」という意見もありました。
定時制では体育大会などの行事が少ないため、仲間と協力し合う場を増やしたいとの声。
「イベントでなくても、授業の中でコミュニケーションをとる機会がほしい」という想いも聞かれました。
一人一人が異なる背景をもちながらも、未来に向かって前向きに考えている姿がとても印象的でした。


4.担当職員の声
ワークショップ終了後、県の総合教育課の渡辺さんと教育政策課の山田さんにもお話を伺いました。
― ワークショップ実施にあたっての思いをお聞かせください。
静岡県の教育は、これまでも「教育振興基本計画」に沿って取り組んできましたが、次期計画の策定では初めて、こどもや若者から直接意見を聞く試みを行いました。
こどもたちが「自分たちの幸せ」や「教育のあり方」についてどう感じているか知ることができる貴重な機会として、私たちも楽しみにしていました。
― 実施を通して印象に残ったことは?
「みんなが幸せになるために必要なこと」を考える際、自分の経験をもとに具体的に話してくれたことが印象的でした。
普段から、自分だけでなく周囲も良い環境であるようにと考えていることが伝わってきました。
― 今後に生かしたい点や課題はありますか?
生徒のみなさんが一人一人、自分にできることを頑張っていたり、困りごとに向き合っていたりする姿がありました。
これからは、少しでも多くのこどもたちがウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に全てが満たされた状態)を感じられるような計画をつくっていきたいです。
ワークショップに参加したこどもたちが夢を語る姿には明るい未来を感じました。
一方で、過去のつらい経験を語る姿にも心を動かされ、同じ思いをするこどもが減るようにと強く感じました。
5.取材を通して感じたこと
今回の取材を通して感じたのは、「こどもの声を聴く」という取組の持つ意味の深さです。
一人一人が自分の思いを言葉にすることで、学校や社会の中でどんなことを感じ、何を大切にしているのかが見えてきました。
特に印象的だったのは、夢や目標を語る中に、日常の中で感じる課題や小さな気づきが自然と織り込まれていたことです。
それは、こどもたちが自分の経験を通して社会を見つめ、少しずつ未来を考えている証のように思えました。
また、行政の方々が一つ一つの声に丁寧に耳を傾け、真摯に受け止めようとしていた姿も印象に残っています。
こうした対話の積み重ねが、より多くのこどもたちにとって「自分の意見が届く社会」を形づくっていくのだと感じました。
【問い合わせ】 県総合教育課 TEL:054-221-3764